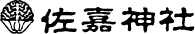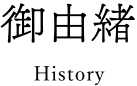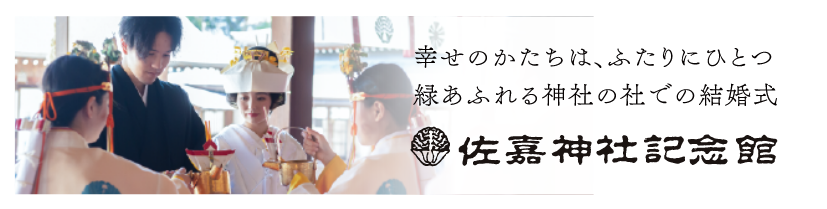佐嘉神社は幕末の佐賀の名君として名高い10代藩主鍋島直正(閑叟)公と11代藩主直大公をお祀りする神社です。
直正公は明治4年(1871)に薨去されましたが、旧藩士民の公に寄せる敬慕の念は厚く、早くも明治6年(1873)には藩祖直茂公を祀る松原神社に公をお祀りする「南殿」が設けられ、明治8年には県社に列せられました。
その後、旧藩士民をはじめ各界の直正公顕彰の動きは日増しに高まり、遂に昭和4年、直正公を祀る佐嘉神社のご創建が決まり、昭和8年9月23日、松原神社南殿から佐嘉神社へご鎮座、同28日には「別格官幣社」に列せられ、勅使参向のもと盛大に列格奉告祭が執り行われました。
昭和23年、11代直大公も当神社に合祀されました。
松原神社は明和9年(安永元年 1772)、佐賀藩第8代藩主鍋島治茂公により藩祖鍋島直茂公をお祀りする「日峯社」として創建されました。治茂公は佐賀藩中興の祖と仰がれ、六府方(殖産興業機関)や藩校弘道館の創設など藩政改革を積極的に進められましたが、その改革の初めにあたり、佐賀藩創業の精神に立ち返るべく、藩祖直茂公を祀る神社を創建されたのです。なお、ご神号「日峯大明神」は、直茂公のご戒名「高伝寺殿日峯宗智大居士」によるものです。
その後、文化14年(1817)に直茂公の夫人彦鶴姫様(陽泰院様)と祖父清久公(利叟様)を合祀し「松原社」と改称、更に明治5年(1872)、初代藩主勝茂公が合祀されました。
明治6年(1873)、それまで春日(現在の佐賀市大和町)の敷山神社でお祀りされていた龍造寺隆信公、政家公、高房公の三柱を新に「北殿」として合祀、同年、幕末の名君十代藩主鍋島直正公の遺徳を偲ぶ旧藩士民の願いによりその御霊を祀る「南殿」が奉祀され、直茂公以下鍋島家4柱を祀る「中殿」とあわせ三つの本殿からなる「松原神社」となり、明治8年県社に列格、大正12年(1923)には最後の藩主、十一代直大公も南殿に合祀されました。
昭和8年(1933)、松原神社西方の浄域に直正公の御霊をお遷しして新たに佐嘉神社が創建され、昭和23年(1948)には直大公の御霊も佐嘉神社に合祀されました。その後昭和38年(1963)、本殿を一殿二座に改築、鍋島家4柱を南座、龍造寺家3柱を北座に祀り現在に至っています。