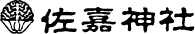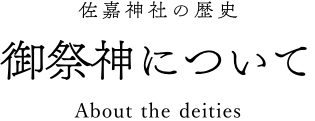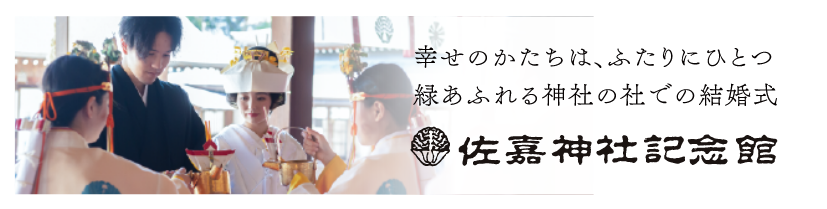鍋島直正公(号 閑叟)は文化11年(1814)、江戸の佐賀藩邸にてご出生。文政13年(1830)弱冠17歳で藩主の座に就かれると鋭意藩政の刷新に努められ、藩校「弘道館」を拡張、長崎には英学校「致遠館」を設けて人材の育成を図り、また救世済民の志厚く、医学館「好生館」(現在の県医療センター好生館の前身)を設け、
初めて種痘を実施するなど西洋医学をいち早く取り入れ、更に欧米列強の我が国への進出を見据え、反射炉を設けて大砲(カノン砲・アームストロング砲)の鋳造に成功、精錬方(理化学研究所)では、蒸気船や蒸気機関車の模型、電信機など製造し、海軍方(三重津海軍所)を設けて近代海軍の養成に努め、我が国初の実用蒸気船「凌風丸」を建造するなど大いに先進技術の摂取・開発に努められ、佐賀藩を薩長土の各藩と共に明治維新の原動力となる雄藩に育て上げ、国家の為にその生涯を捧げられました。
公の数々の御事績にちなみ、文化・産業・学問・交通などの神として、広く崇敬を集めています。
鍋島直大公は直正公の嫡男として弘化3年(1846)佐賀城にてご出生。文久元年(1861)16歳で藩主となられました。
公は父君直正公の御志を継いで同様に藩政刷新と殖産興業に努められ、慶応2年(1868)、我が国が初めて参加したパリ万国博覧会に幕府や薩摩藩と共に代表を送り有田焼などを出展、戊辰戦争では新政府軍に参加し、自ら指揮を執られ佐賀藩兵を率いて各地を転戦されました。
明治2年(1869)には薩長土の各藩主とともに版籍奉還の上表書を奉呈、また同年大名家から唯一議定職に補せられ、明治4年(1871)岩倉使節団の一員として渡航、引き続き11年までイギリスに留学されました。
帰国後は外務省御用掛となり、明治13年には駐イタリア王国特命全権公使としてイタリアに駐在、明治15年帰国の後は宮内省式部頭、元老院議官、宮中顧問官などを歴任される一方、大日本音楽会の会長や皇典講究所所長、国学院大学長などを務め、我が国の文化の興隆、伝統文化の保存に尽力され、また大正2年( 1913)には佐賀県で最初の公共図書館「佐賀図書館」を建設されるなど郷土佐賀の文教発展にも大いに力を尽くされました。
当時第一級の文化人として知られた公は、父君直正公同様に文化の神として広く崇敬を集めています。